4年生
大洲観光遠足に行ってきました!
2学期の3,4年生の遠足は、大洲城→鵜飼い見学→屋形船体験→冨士山公園という、大洲市堪能ツアーでした。
大洲城では、木造建築の雰囲気や、刀や甲冑を楽しみました。天守閣から見える肱川周辺の風景も美しかったです。また、子供たちは急すぎる階段を楽しんでいました。




うかいレストプラザでは、実際に鵜の様子を見せてもらいました。思ったより迫力のある面構えで驚きました。何人かの子供は、餌やり体験もさせてもらいました。投げた魚を素早くキャッチする鵜の姿にみんな興奮していました。


屋形船体験では、間近に見える肱川の穏やかな流れを楽しんでいました。



屋形船体験の動画は、下の「屋形船イラスト」をクリックしてご覧ください!
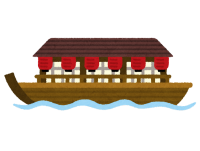 ←こちらをクリックしてください。
←こちらをクリックしてください。
冨士山公園では、展望台で昼食をとった後、山頂を目指して登ったり、ふれあい公園で体を動かしたりして、大いに楽しみました。





2学期の遠足は、全員が無事で楽しむことができました。
10月27日(木) 秋の読み聞かせ
今日は2学期2回目の読み聞かせでした。秋も深まり、もうすぐハロウィーンということもあり、「読み聞かせdandan」の皆さんの出立も、魔法使いに!!いつも子供たちを楽しませていただき、ありがとうございます!子供たちも楽しい絵本に、夢中になりました。
子供たちの一日平均の読書時間が、10分未満という統計がありました。いつも忙しい子供たちの生活が反映されていることもあるのですが、何とか図書に触れる環境も整えて行きたいと思います。秋の夜長、大人も一冊、本を手に取ってみてはいかがでしょうか・・・。






10月26日(水) 全校レクリエーションスポーツ大会
今日は、愛媛県レクリエーション協会の皆さんに来ていただき、全校レクリエーションスポーツ大会が行われました。パラリンピックでおなじみの「ボッチャ」をはじめ、「フライングディスク」や「ラダーゲッター」など、3種目を楽しみました。
年齢や体格にかかわらず、みんなが楽しめるスポーツとあり、1年生から6年生まで全員で盛り上がることができました!「ボッチャ」は、独特の重みと手触りの球を、白球(目標球)に近づけようと対戦します。白球に近づくたびに、大歓声が上がりました!様々な障がい者スポーツに触れることにより、誰とでも和を保ちながら共通の楽しみを感じられる子供たちになってほしいと思います。






10月25日(火) 町内小中学校音楽会
今日は、久しぶりに子供たちの演奏による、町内小中学校音楽会が行われました。残念ながら感染防止対策のため、保護者の皆様には会場でお聞きいただけず、大変申し訳ありませんでした。4・5年生の子供たち、張り切って参加し、すばらしい演奏を会場の皆さんに届けました。
放課後遅くまで毎日続けた練習は、きっと大変だったことと思いますが、全員で一つのことに取り組んだ経験は、きっと、子供たちにとって大切な思い出になったことと思います。応援していただいた保護者の皆様、ありがとうございました。五十崎小学校の演奏を、下のQRコードを読み取って、ぜひお聞きください。







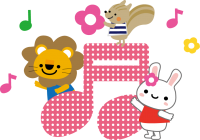
10月24日(月) 交通安全教室
今日は、延期になっていた「交通安全教室」を、1~3年生の子供たちが行いました。大洲警察署の方や五十崎駐在所連絡協議会の皆さんにお越しいただき、安全な道路の通行の仕方を中心に教えていただきました。いつも通り慣れている道ですが、改めて安全について確認しながら通行しました!これから日没の時刻もどんどん早くなります。どんな時でも、安全に気を付けて過ごすことができるよう、ご家庭でもお声掛けください。




10月20日 生き物ビンゴ
3年生は総合の時間に五十崎の自然について調べています。今日は講師の松田さんをお招きし、小田川で生き物ビンゴをしていただきました。小田川で見られる昆虫や鳥などをビンゴ形式で探し、子どもたちは夢中になっていました。よく見かけるバッタやチョウだけでなく、セキレイやカワセミ、アオサギなどなかなか見ることができない鳥も見ることができて、とても貴重な体験になりました。また、ショウリョウバッタのからだのつくりも解説していただき、学びも深まりました。



1年生
10月19日 パトリシア先生
算数では「かたちづくり」の学習をしています。今日は、影絵の形を観察して、色板を並べたり枚数を数えたりする活動でした。パトリシア先生が来てくださったので、特別に、色板の枚数を英語で数えました。影絵の形に合わせて色板を並べ、数も英語で言えた児童はパトリシア先生に「Perfect」と褒めてもらい、とても嬉しそうでした



10月18日(火) 響けハーモニー!音楽会演奏曲披露!
4・5年生が、来週行われる内子町小中学校音楽会で発表する曲を、全校のみんなに披露しました。
9月から練習を重ねてきた「ふるさとの色」は、NHK四国応援ソングとして耳にされたことがあるのではないでしょうか。演奏や合唱を分担し、みんなで心を一つに練習してきました!すてきな歌声と演奏が、会場の「スバル」でもいっぱいに広がることと思います!応援していますよ!頑張ってね!



4年生